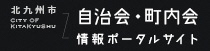周辺の名所・旧跡THE NOTED PLACES
到津八幡神社
 |
神功皇后が新羅渡航から帰還の時、宇美の里で応神天皇を産み、そして長門の豊浦宮への途中、この地に船を着けた。後に祠を建て、皇后の和魂を祀ったのが社の起源といわれている。社家は祠宇草創の年忌を、約1435年前の欽明天皇の時代と伝えている。 また神功皇后がこの前に流れる川の水を汲み産湯に使ったことから、人々は安産を願うようになったと云われている。 現在この川は板櫃川と呼ばれているが、鳥居付近だけ「産川」と云われていた。文治4年(1188年)、宇佐八幡大神を合祀し、神主は宇佐八幡宮の支族が務めることとなった。 永禄4年(1561年)大友宗麟が宇佐八幡宮を攻め全て焼き払ったため、宇佐八幡宮の神官たちは神輿を守護して、この到津八幡神社遷座することとなった。そして天正11年(1583年)までの23年間、この地に留まっていた。また、この地も戦乱に見舞われ、到津八幡宮も荒廃し宝器古文書等もことごとく紛失してしまった。 慶長5年(1600年)、豊前国城主となった細川忠興は、本殿を始め諸殿を再建するとともに、小倉城の産土神として祀った。その後、寛永9年(1632年)小倉城主となった小笠原忠真も産土神として祀った。 大正14年、県社昇格願を提出し認可される。なお現在の社殿は、昭和49年に大修理されたものである。 |
板櫃川古戦場跡
  |
天平11年(740年)9月、 藤原広嗣は、筑前国遠賀郡(現岡垣町)に本営を置き、当時各郡におかれていた軍団を主に約一万騎をもって律令政府軍の大将大野東人の率いる一万七千騎と板櫃川で対峙した。 広嗣は律令政府軍に勅使がいることを知り、問題をあいまいにしたまま戦線を離脱し大敗した。 おそらく板櫃川下流域が戦場と考えられる。当時は水量が多く、川幅が約500mあったと云われている。 |
到津の森公園
 |
「到津の森公園」は、西日本鉄道㈱が運営していた「到津遊園」を、北九州市が引き継ぐ形で開園した市営の動物園である。「到津遊園」は、西日本鉄道㈱の前身会社である九州電気軌道㈱が、創立25周年の記念事業として昭和7(1932)年、当時の小倉市到津の自然丘陵地に遊園地として開園。翌昭和8(1933)年に動物園を併設した。 長年多くの市民に親しまれてきたが、施設の老朽化や娯楽の多様化等に伴い利用者が減少、経営が悪化し、平成10(1998)年4月21日、「到津遊園」の閉園が発表された。しかし、52団体、およそ26万人もの存続署名が市を動かし、市が運営を引き継ぐことが決定。平成12(2000)年5月31日の閉園、その後の整備をへて、平成14(2002)年4月13日、「到津の森公園」として装いもあらたに開園したものである。 園内では、およそ100種500点の動物を飼育・展示しており、四季折々の草花や、観覧車・メリーゴーラウンド等の遊具も楽しむことができる。 |